Vol.1
下田昌克さん
[イラストレーター]
「旅」、「めぐる」をテーマに掘り下げる『働く人のライテンダー』。第1回目は、その2つのキーワードを体現しているといっても過言ではない下田昌克さん。イラストレーター・画家として一躍名を広めたのは、旅先で出会った人を色鉛筆で描きながら世界を2年間放浪した自身初の旅行記「PRIVATE WORLD」がきっかけであり、ハンドメイドで制作している恐竜作品は、パリコレのランウェイを歩いて世界の8都市を巡回した。まさに「旅」と「めぐる」を突き進んできた下田さんに聞く、ルーツとターニングポイント、そして、これからの旅について。
「人生、どうつながって、
どう転がっていくかわからない。
わからないから楽しい」
- --いつから絵を描いていたんですか?
- 幼稚園? とかそれぐらいじゃないですかね。鉛筆と紙を渡したらおとなしくしているような子供で、将来の夢は何かと聞かれたら「手塚治虫になりたい!」って言ってました。
- --漫画家じゃなく、手塚治虫(笑) そのころからポートレートを?
- 人の顔を描くようになったのは、大人になって旅行をするようになってからですね。当時描いていたのは、怪獣や恐竜、ロボットや戦隊モノがほとんど。小学生の頃から1人で映画に行くことを許してくれる親だったので、『ET』や『ブレードランナー』、スターウォーズ シリーズなどのSF映画からはモロに影響を受けました。
- --画家になろうと真剣に考えたのはいつですか?
- 高校受験のときですかね。といっても、真剣にではなく。勉強が嫌いで、頭もよくなくて(苦笑)。絵ばっかり描いていた僕に、中学校の美術の先生が、「兵庫県立明石高等学校の美術科、受けてみないか? 学科試験ないぞ」って言われて、「学科試験がない」っていうひと言に惹かれて受けたら運よく合格したんです。
- --高校生活はどんな感じでしたか?
- どうだろ。楽しかったけれど、挫折を突きつけられた感じでしたね。クラスのみんなが美大を目指していて。デッサンの授業とかみんな上手で全然ついていけず……。美術だけじゃなく勉強も落第スレスレで、美大に進学するのは無理だよと高校入学して早々に言われていました。

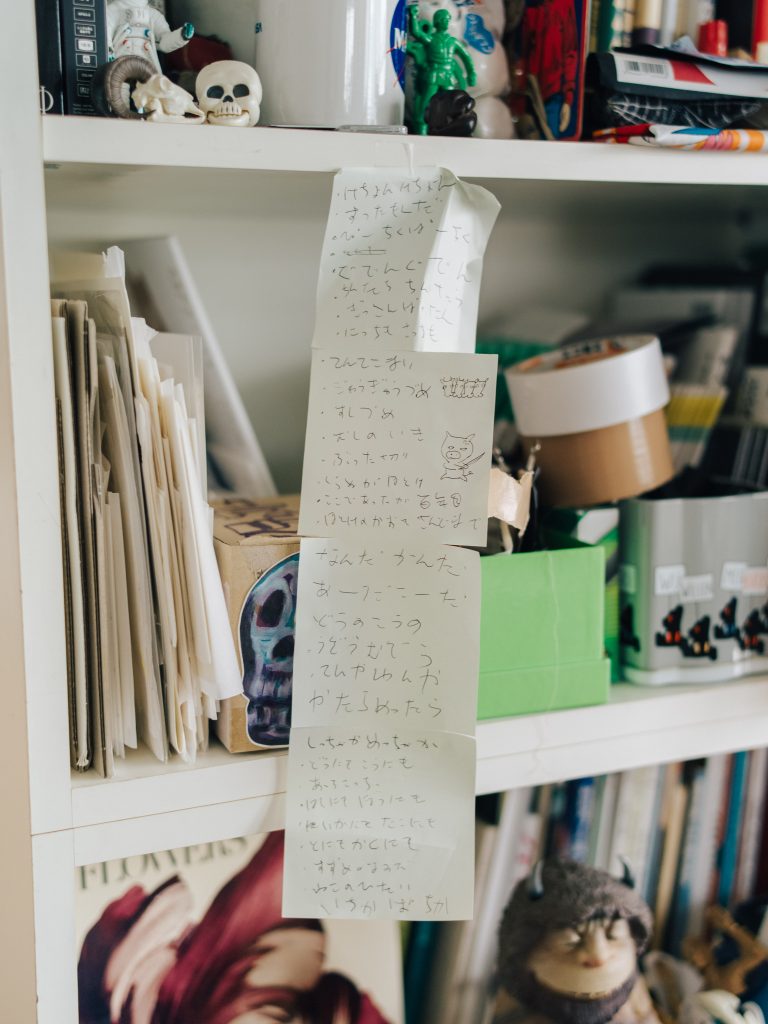


- --そこからどんな流れでデザインの専門学校を選ばれたんですか?
- 理由は簡単。渋谷区だから(笑)。東京で遊びたかった。高校2年で油絵や彫刻などの専攻を決めるとき、絵が下手でも大丈夫かなと思ってデザインを選んで。渋谷区にある桑沢デザイン研究所を知って、とにかく上京して遊びたい一心で決めました。
- --場所ありき(笑)
- そうそう。でもね、3年通って卒業して就職したもののすぐに辞めて、アルバイトをしても続かず。今度こそ!と意気込んでデザインの会社に就職しても、あっさりクビになる始末。「明日から、もう来なくていい」って。多分言うことを聞かなかったからでしょうね。一番下っ端なのに、仕事を選んで偉そうだったからかなぁ。
- --クビになるって久しぶりに聞きました。
- 本当ですよね。それからは、クビになって何をしたらいいのかわからなくなって、いったん働くということから距離を置いてみようと考えたんです。今も作業場として使っているアパートを友達に又貸しして、「2〜3ヶ月いなくなるから住んでおいて」って言って、自転車にテントや寝袋を積んで、なんとなく出発したんです。そのころは若くて体力もめちゃくちゃあったから、日本海を経由して、実家がある神戸を目指し、寄り道ばかりしながら自転車でぷらぷらしていました。
- --その期間中は、まったく働かなかったんですか?
- 働くことから距離を置いたのに、道中で知り合った人からスプリンクラーの設営の日雇いバイトがあると誘われたり、国道沿いを走っていたら、野菜の収穫をしているから働かない?って言われたり。そんなこんなでアルバイトを繰り返していたら、お金が貯まってきたんです。
- --実際、いくら稼いだんですか?
- 100万円です。貯まったときに、1ヶ月くらいでパーっと使い切る贅沢をしよう! と決めて旅行に出たのが1994年、26歳のときのこと。北京ダックを食べるという目的だけを決めて出発し、中国からチベット、ネパール、インド、気づいたら、ヨーロッパに辿り着いていて、結局、帰国したのは2年後でした。
- --その2年の記録を詰め込んだ旅行記「PRIVATE WORLD」、最高でした。2002年の発売当時、ヴィレッジヴァンガードの下北沢店のサブカルコーナーで「衝撃作!!」と大々的に紹介されていて、確かに読んだ瞬間の衝撃がハンパじゃなかったのを覚えています。そもそも帰国されてから、どんな経緯で出版に至ったんですか?
- 旅で出会った人をひらすら描いていたスケッチブックを『週刊アサヒグラフ』の編集者に見てもらって1年間連載させてもらうことになり、その後『月刊アウトドア』でも連載をさせてもらって、その流れで、ありがたいことに本を出さないかと誘ってもらったんです。
- --こう言っちゃあれですが、レイアウトが、何度見ても、とんでもないです。
- 今思うと、出版社がよく出してくれたと思います(笑)。めちゃくちゃですよね。編集者と、アートディレクターの長友啓典さんから「とりあえず、つくりたいように最初から最後までつくってみて」と言われて、出版社の地下室に、カラーコピー機と一緒に軟禁状態にされたんですよ。旅で書いた日記や、現地でプリントした写真、ポートレートや風景のイラストをコピーしまくって切って貼ってそのまま入稿しているから、もうしっちゃかめっちゃかです。
- --だから奥付にカラーコピー機のモデル名が載っているんですね(笑) この本を出版してから仕事はガラリと変わりましたか?
- ですね。かなり。こんな思いもよらない方向から来るのか、という仕事が増えました。とりわけ小説の挿絵は嬉しかったです。どうやって描こうかと悩むのがもう楽しくて楽しくて。挿絵で思い出深いのは、山崎豊子さんが晩年に出された『運命の人』と『約束の海』の2作。挿絵の仕事は作家の方と直接話すことはあまりなかったんですが、山崎さんは、女性のメイクや、男性のネクタイなど、時代背景と合わせて細かく教えてくれて、一枚ずつ感想を伝えてくれて。そういうやりとりが本当に面白かったし勉強になりました。
- --映画の美術をやられたのも出版後ですよね?
- そうそう。美術監督の都築雄二さんに声をかけていただいて2007年公開の映画『クローズド・ノート』に参加させてもらいました。まさか自分が大好きな映画に微力でも関われる日が来るとは!と感慨深かったですね。あと、照明や美術のスタッフと東宝の作業場で集まっていたとき、映画『ステキな金縛り』のスタッフの方がいて、「今、法廷画を描く人を探しているんだけど、下田くん、やる??」って言われて、「やります!」という流れで“幽霊が見える法廷画家の描くの絵”を描かせてもらいました。どうつながって、どう転がっていくかわからない。結構楽しいです。



「遊んでいるだけなんですよ。
誰にも頼まれていないのに、恐竜つくってる。
それだけなんです」

- --ここにいる恐竜たちも旅をしていますよね。そもそも何がきっかけでつくるようになったんですか?
- 国立科学博物館で開かれた『恐竜博2011』ですね。そこに展示されていた骨格標本がめちゃくちゃかっこよくて。興奮した状態のまま買い物する気満々でミュージアムショップに行ったら、その時は欲しいものが1つもなかったんです。
- --欲しいものが売ってないから自分でつくったんですか?
- そうですね。恐竜博から家に帰って、絵を描くためのキャンバス生地を丸めて角とかつくっていたら楽しくなっちゃって。自分の頭にあてながらつくっていると、仮面みたいにかぶれるものができたんです。かぶったら平面にはない興奮があって、原始的で動物的で、なんというか、強くなったような不思議な気分。その日から”自分がかぶる”という馬鹿馬鹿しいコンセプトでひたすらつくり続けました。
- --すごい瞬発力ですね。ミシンの経験はあったんですか?
- いや、まったく(笑)。今も、下糸と上糸の調整がわかりません。最近になって、指抜きキャップという存在を知りました。ところどこと茶色いしみがついているんですが、あれは僕の血です。ブッ刺しまくって痛かったなぁ。あと、リッパーという便利な道具を知ったのもつい先日の話。それまでは途方もない時間をかけてカッターで切っていました。
- --「PRIVATE WORLD」のときと同様、手作業だからこそ訴えかけるモノの強さや味わいがあるんですね。ちなみに、キャンバス素材に特別な意味はあるんですか?
- いや、むしろ僕にとっては一番意味を持たない生地です。当たり前に身近にあったもの。だから好き勝手にいじりやすいのかな。



- --恐竜たちで本を作る予定は最初からあったんですか?
- いやいや、谷川俊太郎さんが助けてくれなければ間違いなく世に出てなかったかもです。絵本の打ち合わせに恐竜を持っていったら、率先してかぶってくれたんですよ。素敵な方ですよね。それから、打ち合わせのたびに一番新しいのを持っていったら、毎回かぶってくれて、谷川さんから、「詩を書くから連載をしよう」と言ってくれたんです。写真は藤代冥砂さんに撮ってもらって、大好きだった雑誌HUGEで『恐竜仮面』が2013年に始まり、翌年から雑誌SWITCHで『恐竜がいた』をやらせてもらいました。
- --そのときはまさか2018-19F/W「コム・デ・ギャルソン・オム プリュス」のランウェイのヘッドピースとして恐竜が採用されるとは思ってないわけですよね。
- もちろん。誰からも頼まれていないのに、自分がかぶるために恐竜をつくっている、ただそれだけでした。
- --コム・デ・ギャルソンの方から連絡が来たんですか?
- そうですね。SWITCH編集部経由で。半信半疑で青山の本社へ行くと、広い会議室に川久保玲さんがお一人でいらっしゃって、挨拶して早々、「2週間後にパリ行ける?」と言われたんです。「行けます!」と答えたものの、パリはパスポートの残りが6ヶ月以上ないとダメらしく、見たらギリギリで……。その足で更新に行きました。パリに持っていった恐竜は15、16体ぐらいかな。頼まれていないのに、いくつか多めに勝手に忍ばせました。
- --冷静に考えると、すごい話ですよね。
- 自分の物欲を満たすためにつくった恐竜たちがパリコレのバックステージにいて。そしてモデルにその恐竜をかぶせている。その状況があまりにも不思議でわくわくしました。
- --それから恐竜たちは世界中をめぐりましたよね。
- 半年後に『コム・デ・ギャルソン』の青山店で恐竜のインスタレーションをした後、ニューヨークとパリの『コム・デ・ギャルソン』。銀座、ニューヨーク、ロンドン、北京、香港、ロサンゼルスの『ドーバー ストリート マーケット』を巡回しました。世界8ヶ所。現地で設営をさせていただけるなんて、とても楽しかったです。
- --世界の頂点とも言える究極の舞台の3年後に、「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™」の2021-22AWパリオートクチュールコレクションでまた恐竜が登場したのは衝撃的でした。
- 僕も同じく(笑)。恐竜の世界巡回が終わって、あぁもうこんな経験は2度とできないんだろうなぁと思っていたら、デザイナーのヴァージル・アブローのアカウントからインスタで直接メッセージが来たんです。「本当に本人?」って聞いたら「そうだよ」って返信があって、「いくつか欲しい」と言ってもらって。「どういうのがいいの?」と返して、「ここはこんな感じ」とか、写真の上に指示が書かれた画像が届いて、そのやりとりが面白かったです。この先また何かあるといいなあ。
「色鉛筆とスケッチブックの代わりに、
iPadを持って旅に出るのも面白そう」

- --これから、下田さんの人生はどう進んでいくんですかね。
- 本当はもっと計画的にやっていけるといいのですが。でもなんか、変化を求めている時期かもしれないですね。恐竜制作に飽きないのは、まだミシンという道具に苦戦しているから。上達したらきっと飽きちゃうんだろうな。自分にとって、便利なものって面白くないんですよ。不便さと格闘しながらむりくりやっつけるぐらいの作業が好きだし、楽しい。最近は、緻密に書ける色鉛筆に慣れちゃったので、不慣れなクレヨンに変えてみたりしています。
- --例えば、作品を売ってみるとか。
- これからできるといいんですが、値段をつけるとか、よくわからなくて。手放すことで、何か新しい発見があるかもしれないと思ったこともあるんですが、売れる、売れないとか、アートの価値も正直わからなくて。あと、血を流しながらつくったから愛着もあって(笑)
- --(笑) 下田さんの「恐竜博」シーズン2、見たいです。
- やってみたいですね。
- --最後に、また旅に出るとしたら、どんな旅をしたいですか?
- 今まで出した旅の本はスマホのない時代のものだから超アナログなんですよね。写真も現地でプリントして、ツールはスケッチブックと色鉛筆。でも、スマホがあるからこその旅もあると最近思うんですよ。最近、画家のデイヴィッド・ホックニーが2020年にiPadで描いた画集を見たんですが、それがホックニーらしさ全開で、手描きじゃないのにデジタルの可愛さがあって。だから、新しいツールを持って旅に出て本を作るのも面白そうだなと。デジタルの旅。面白そう。よし、早速iPad買います!


text:Kyosuke Nitta
photo:Kazumasa Harada
photo:Kazumasa Harada

PROFILE
下田昌克Masakatsu Shimoda
1967年、兵庫県生まれ。1994年から2年間、世界中を無計画で放浪。旅先で出会った人々のポートレイトを色鉛筆で描き、そのときの日記を斬新なカラーコピーでまとめた「PRIVATE WORLD」をきっかけにイラストレーター・画家としてのキャリアを本格化。2011年からはミシンを駆使して恐竜のかぶり物をつくり始め、2018年には「コム デ ギャルソン・オム・プリュス」のショーにヘッドピースとして採用。「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™」の2021-22AWパリオートクチュールコレクションにも恐竜が登場し、モードシーンの話題をかっさらった。谷川俊太郎との共著に「恐竜人間」(パルコ出版)、「恐竜がいた」(スイッチ・パブリッシング)。「PRIVATE WORLD」(山と渓谷社)は、読むたびに旅をしたくなる。

